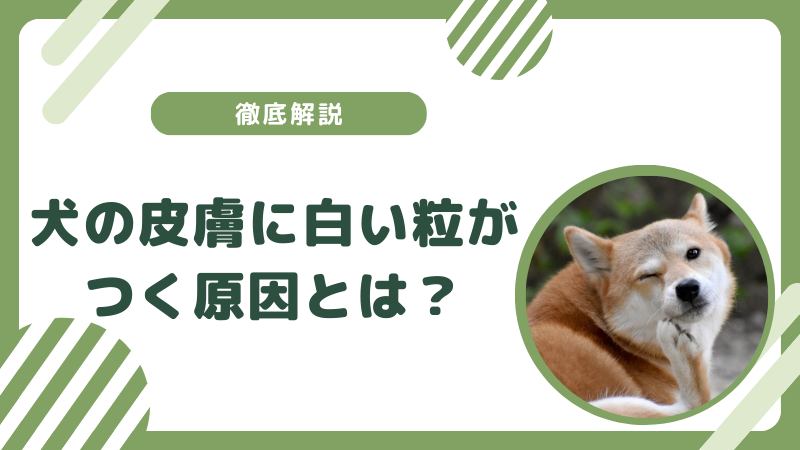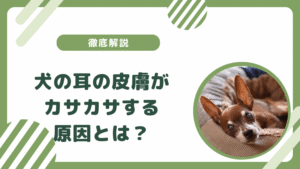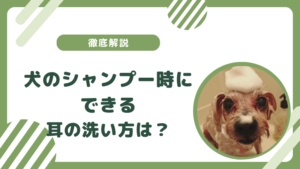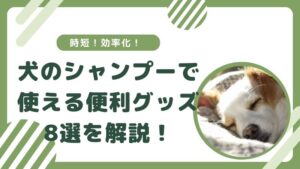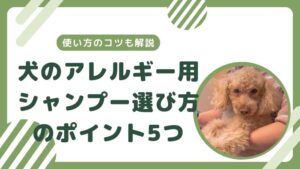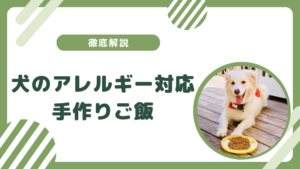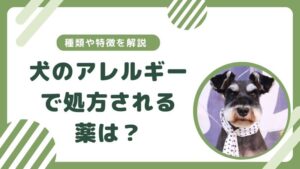「愛犬の皮膚に白い粒がついている・・・」
「白い粒の原因は?つかないように対策できる?」
と悩んでいる飼い主さんも多いのではないでしょうか。
犬の皮膚に現れる白い粒は乾燥によるフケから皮膚病のサインまで、原因はさまざまです。
放置すると症状が悪化することもあるため、早期発見と正しいケアがとても大切です。
この記事では、白い粒ができる原因や対処法、日常的にできる予防法まで詳しく解説します。
愛犬の皮膚にできる白い粒について知りたい方は、ぜひ参考にしてくださいね。
南柏たなか動物病院では、日本で数人しかいないアジア獣医皮膚科の専門医が病院訪問を担当しており、あらゆる皮膚の病気の治療が可能です。
院内は居心地の良い環境や話をしやすい雰囲気づくりを意識しており、飼い主様の不安に寄り添いながら診察しておりますので、お気軽にご相談ください。
\愛犬の皮膚に異変を感じたら/
犬の皮膚に白い粒が現れる原因5つ
犬の皮膚に白い粒ができる主な原因は、以下の5つです。
・フケ(乾燥性・脂漏性)
・マラセチア菌による皮膚炎
・ノミやダニの卵・フン
・脂漏症
・皮膚腫瘍や嚢胞
順に解説していきます。
原因①:フケ(乾燥性・脂漏性)
犬のフケは、古い皮膚細胞が剥がれ落ちたものです。
乾燥性フケは空気の乾燥や不適切なシャンプー、栄養不足などが原因です。
さらに皮膚がカサカサしており、毛をかき分けるとパラパラと白い粉が落ちます。
一方、脂漏性フケは皮脂の過剰分泌によって起こります。
皮膚がベタつき、特有の臭いがするのが特徴で、白い粒が毛にくっついているように見えるのが特徴です。
乾燥が原因の場合は保湿ケアが有効ですが、脂漏症が疑われる場合は動物病院での治療が必要です。
原因②:マラセチア菌による皮膚炎
マラセチア菌は犬の皮膚に常在するカビの一種ですが、免疫力が低下したり皮脂が過剰に分泌されたりすると増殖し、皮膚炎を引き起こします。
このとき皮膚に見える白い粒は、かさぶたや剥がれ落ちた角質です。
マラセチア皮膚炎になると皮膚がベタつき、強い体臭がすることが特徴です。
また、湿気の多い季節や耳の裏、お腹などの皮膚が薄い部分に症状が出やすいため、皮膚が赤くなったり犬が頻繁に体をかいたりしている場合は注意しましょう。
原因③:ノミやダニの卵・フン
白い粒が毛の根元にくっついている場合、ノミやダニの卵の可能性があります。
ノミの卵は白っぽく楕円形で1ミリ程度と非常に小さいですが、毛の根元にまとまって付着していることも。
また、ノミのフンは黒い粒状ですが、水に濡らすと血がにじむように赤くなるため白い粒と混在している場合もあります。
犬が激しく体をかいていたり、被毛が抜けたりしている場合はノミ・ダニが寄生している可能性が高いため、早めに駆虫薬を使用するなどして対策しましょう。
原因④:脂漏症
脂漏症は、皮脂の分泌異常が原因で起こる皮膚病です。
皮膚が過剰に皮脂を分泌して毛穴が詰まることで、白い粒のようなフケやかさぶたができます。
脂漏症には、乾性脂漏症(皮膚がカサカサしてフケが出るタイプ)と湿性脂漏症(皮膚がベタついて脂っぽいタイプ)があります。
白い粒が目立ったり皮膚が赤く炎症を起こしたりしている場合は、脂漏症の可能性があるため、動物病院で皮膚の状態を確認してもらいましょう。
原因⑤:皮膚腫瘍や嚢胞
白い粒が固く触っても取れない場合は、皮膚腫瘍や嚢胞の可能性があります。
嚢胞は皮膚の下に袋状のものができ、そこに皮脂や角質が溜まることでできます。
一方、腫瘍の場合は良性と悪性があり、特に粒が短期間で大きくなっている場合は早急な診察が必要です。
腫瘍や嚢胞は素人判断が難しいため、白い粒が固くしこりのように感じられたら、すぐに動物病院へ連れて行きましょう。
犬の皮膚に白い粒を見つけたときの対処法
愛犬の皮膚に白い粒を見つけたとき、驚いてしまうかもしれませんが、まずは落ち着いて状況を確認することが大切です。
白い粒ができた原因を正しく把握するためには、冷静に観察し必要に応じて専門家に相談することが重要です。
まずは、白い粒がどのような状態なのかをじっくりと観察しましょう。
白い粉のようにポロポロと落ちるのか、それとも毛の根元にくっついているのかによって原因は異なります。
また皮膚の赤みや腫れ・ベタつき・独特な臭いがあるかどうかも確認してください。
さらに犬が頻繁に体をかいていたり、噛んだりしている場合は、かゆみを伴う皮膚トラブルの皮膚トラブルは早期発見と早期治療が鍵です。
些細な変化でも軽く考えず、愛犬の健康を守るために積極的に行動しましょう。
南柏たなか動物病院では、犬や猫のあらゆる症状のお悩みに寄り添いながら診察いたします。
予約の際は、WEB・お電話でしていただくことで待ち時間が少なくすみます。
\愛犬のためには早期発見が大切/
自宅でできる予防法3つ
犬の皮膚に白い粒ができないようにするには、以下のような自宅でできる予防法を実践する必要があります。
・スキンケアを徹底する
・ノミ・ダニ対策を習慣化する
・ブラッシングで早期発見する
毎日ケアして、皮膚に白い粒がつくのを予防しましょう。
予防法①:スキンケアを徹底する
犬の皮膚は人間よりも薄くデリケートです。
乾燥や脂漏症を防ぐために、日常的なスキンケアを心がけましょう。
乾燥性フケを予防するためには、皮膚の保湿が重要です。
犬用の保湿スプレーやクリームを使い、散歩後やシャンプー後に皮膚が乾燥しやすい部分をケアします。
特に冬場は空気が乾燥するため、念入りに保湿しましょう。
シャンプーの選び方と頻度も重要です。
月に1〜2回のシャンプーを目安にし、皮膚に優しい低刺激の犬用シャンプーを選びましょう。
お湯の温度は37~39℃程度のぬるま湯にし、熱すぎるお湯は皮脂を奪うため注意が必要です。
シャンプー後は必ずタオルで優しく拭き、ドライヤーを使って皮膚までしっかり乾かします。
濡れたままだと菌が繁殖しやすくなるので、完全に乾燥させることが大切です。
犬のシャンプーについて詳しく知りたい方は、こちらの記事も参考にしてくださいね。
「犬のシャンプーで注意すべきポイントとは?正しい洗い方と頻度を徹底解説」
予防法②:ノミ・ダニ対策を習慣化する
ノミやダニは皮膚に白い粒(卵やフン)を残し、かゆみや皮膚炎を引き起こします。
これを防ぐためには、日常的な予防や動物病院で処方されるノミ・ダニ予防薬が効果的です。
スポットオンタイプ、内服薬タイプなどがありますが、市販薬よりも動物病院で処方されるものがよいでしょう。
また、室内環境の清潔さを保つことも予防になります。
散歩後には犬の足を拭き、寝床や毛布を週に1回洗濯するなど、室内環境を清潔に保つことも大切です。
特にカーペットやソファはノミ・ダニが隠れやすい場所なので、掃除機を丁寧にかける習慣をつけましょう。
予防法③:ブラッシングで早期発見する
ブラッシングは抜け毛を取り除くだけでなく、皮膚の異常を早期発見する重要な時間です。
毎日ブラッシングすることで、皮膚の状態をチェックし、白い粒がないか確認できます。
特に毛の根元や耳の裏、お腹周りなどは白い粒(ノミの卵やフケ)がつきやすい場所なので、丁寧にブラシを通しましょう。
また毛玉ができると皮膚が蒸れ、菌が繁殖する原因になるため、こまめにブラッシングを行うことも大切です。
まとめ:日常的なケアで愛犬の健康を守ろう!心配な場合は南柏たなか動物病院へ行こう
犬の皮膚に白い粒が現れる原因はさまざまですが、日常的なケアで多くのトラブルを予防できます。
毎日のブラッシングで異常をチェックし、スキンケアやノミ・ダニ予防を徹底することが重要です。
もし白い粒が増えたり、かゆみがひどくなったりした場合は迷わず動物病院を受診しましょう。
南柏たなか動物病院では、皮膚科専門医の診察や予防接種も受け付けています。
少しでも愛犬の異変を感じた場合は、お気軽にご来院ください。
WEB・お電話からの予約優先制を取り入れており、事前に予約いただくことで待ち時間を短縮できます。
\愛犬の皮膚に心配事があるなら/