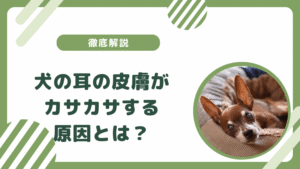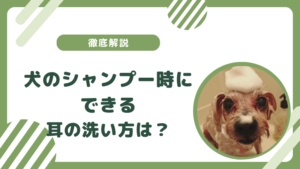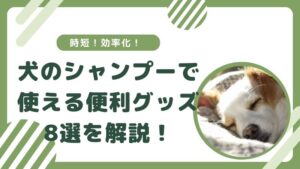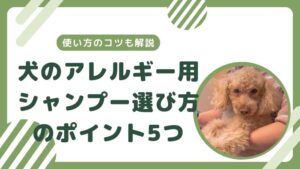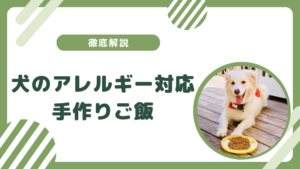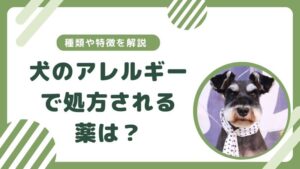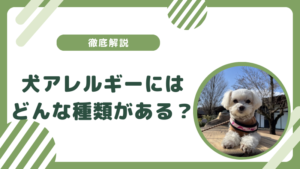「愛犬の皮膚に内出血がある…」
「内出血が現れてしまう原因が知りたい!」
と悩んでいませんか。
犬の皮膚に現れる内出血は打撲などの軽いものから、血液や免疫に関わる重大な疾患のサインまで原因が非常に幅広く、見た目だけでは判断が難しい症状のひとつです。
そのため、愛犬の皮膚に現れた内出血は大丈夫なのか不安になる飼い主さんも多いのではないでしょうか。
この記事では、犬の皮膚に内出血が現れたときに考えられる症状の特徴や原因などを詳しく解説します。
愛犬の内出血について悩んでいる方は、ぜひ参考にしてくださいね。
南柏たなか動物病院では、日本で数人しかいないアジア獣医皮膚科の専門医が病院訪問を担当しており、あらゆる皮膚の病気の治療が可能です。
院内は居心地の良い環境や話をしやすい雰囲気づくりを意識しており、飼い主様の不安に寄り添いながら診察しておりますので、お気軽にご相談ください。
\愛犬の皮膚に異変を感じたら/
犬の内出血が皮膚に見られたときに確認すべき症状3つ
愛犬に内出血があるかも?と感じたら、以下の症状を確認しましょう。
・皮膚内出血の見た目と色の状態
・内出血が発生した部位
・軽度の内出血と重篤な病気を見分ける
少しでも心配になったらまずは、確認して症状を把握してくださいね。
確認すること①:内出血の見た目と色の状態
犬の皮膚に現れる内出血は人間のあざと似た見た目をしており、色は赤や紫、黄褐色などさまざまです。
これは、時間の経過によって血液が分解されていく過程で色が変化していくためであり、急性のものほど鮮やかな赤や紫色が目立ちます。
また、出血の形状は点状・斑点状・広範囲のあざ状などがあり、押しても消えず皮膚表面には傷がないのが大きな特徴です。
確認すること②:内出血が発生した部位
内出血は体のどこにでも発生してしまいますが、特に毛が薄く皮膚が柔らかい部位に集中しやすい傾向があります。
よく内出血が現れる部位は以下の通りです。
・お腹や胸の皮膚
・太ももの内側やわき腹
・耳の内側や眼の周辺
これらの部位は摩擦や衝撃の影響を受けやすく、日常生活の中でのちょっとした接触や打撲が原因となる場合もあります。
また、これらの部位は視認性が高いため、日々のスキンチェックに最適なポイントです。
確認すること③:軽度の内出血か重篤な病気か
軽度の打撲や一時的な外的要因による内出血であれば、数日〜1週間ほどで自然に薄くなり、やがて消えていきます。
しかし、以下のような特徴が見られる場合は、重大な病気の可能性があるため注意が必要です。
・原因が思い当たらないにもかかわらず出血している
・複数箇所に出現している、または左右対称に出ている
・出血が増え続けている、色が濃く変化している
・食欲不振、元気がない、ふらつきなどの全身症状を伴う
このような場合は自己判断で様子を見るのではなく、速やかに動物病院で診察を受けましょう。
犬の内出血が皮膚に現れる主な原因3つ
犬の内出血が皮膚に現れる主な原因は、以下の3つです。
・免疫介在性血小板減少症
・播種性血管内凝固
・毒物摂取による中毒症状
ひとつずつ順に解説していきます。
原因①:免疫介在性血小板減少症(IMTP)
免疫介在性血小板減少症(IMTP)は、犬の免疫システムが誤って自分の血小板を攻撃・破壊してしまう病気です。
血小板は出血を止めるために不可欠な要素であり、大幅に減少するとちょっとした衝撃でも出血が止まらなくなり、皮膚内出血が多発するようになります。
主な症状は以下の通りです。
・点状出血(耳の内側・お腹などに多発)
・歯ぐき・舌からの出血
・血尿・血便
・元気がなくなる、食欲の低下
・発熱や軽いふるえ
この病気は感染症やワクチン接種後、腫瘍などをきっかけに突然発症することもあります。
重症化すると命に関わるため、内出血が複数箇所に見られたら、すぐに血液検査を受けましょう。
原因②:播種性血管内凝固(DIC)
DIC(播種性血管内凝固)は感染症・外傷・中毒・膵炎・熱中症など、さまざまな重篤な疾患に続発して発症する合併症です。
体内の血液が一斉に凝固を始め、その後凝固因子が枯渇してしまい、出血が止まらなくなり危険な状態になってしまうこともあります。
主な症状は以下の通りです。
・広範囲にわたる皮下出血
・鼻血・血尿・血便などの多発的な出血
・虚脱、けいれん、黄疸、呼吸困難
・急激な意識低下や体温の異常
発見が遅れると致命的になるため、複数の出血と同時に全身の異常が見られる場合は、緊急で動物病院に搬送しましょう。
原因③:毒物摂取による中毒症状
家庭や近隣の建物で使われている殺鼠剤の中には、「ワルファリン系(抗凝固剤)」と呼ばれるタイプの毒物が含まれていることがあります。
犬が誤って摂取してしまった場合、体内の血液が固まりにくくなり、皮膚や内臓に出血が広がる中毒症状が引き起こされます。
主な症状は以下の通りです。
・突然の皮膚内出血(原因不明)
・鼻血、血尿、便に血が混じる
・ぐったりして動かない
・呼吸が浅くなる
・歯ぐきが真っ白になる
このような場合は、解毒剤(ビタミンK1)による早期治療が命を救うカギとなるため、心当たりがある場合は迷わず動物病院へ連絡しましょう。
南柏たなか動物病院では、犬や猫のあらゆる症状のお悩みに寄り添いながら診察いたします。
予約の際は、WEB・お電話でしていただくことで待ち時間が少なくすみます。
\愛犬のためには早期発見が大切/
犬の内出血が皮膚に出たときの動物病院を受診すべきポイント
犬の内出血は、場合によっては自然に治癒することもありますが、以下のような兆候が見られる場合は早急な診察が必要です。
・内出血が急激に広がっている
→ 単なる打撲ではなく、体内で止血機能が崩壊している可能性もあり、放置すれば命の危険もある。
・複数箇所に出血がある(皮膚・歯ぐき・鼻・便・尿など)
→ 出血傾向のある重篤な病気(IMTPやDICなど)の疑い。全身性の異常を示すサインです。
・犬が元気をなくし、ぐったりしている
→ 全身の血流や酸素供給がうまくいっていない状態。貧血や内臓出血も考えられます。
・舌や歯ぐきが白っぽい・青白い
→ 明らかな貧血のサイン。酸素不足が起きている証拠であり、非常に危険です。
・出血が止まらない、血がにじむ
→ 血液の凝固異常が起きている可能性。自己判断せず、すぐに動物病院へ行きましょう。
どのサインも「様子を見てよくなる」という可能性は極めて低く、悪化すれば手遅れになることもあるため、少しでも該当する症状があればすぐに受診してください。
犬の内出血が皮膚にできる予防と再発を防ぐための具体的な対策5つ
愛犬の内出血を防止するには、以下の対策をおこないましょう。
・生活環境を見直して事故を予防する
・毎日の健康チェックで早期発見につなげる
・食事と栄養管理を徹底して体の内側から強化する
・安全対策して毒物誤飲を防ぐ
・定期的な健診で異常を早期に発見する
早めに対策することで内出血を防げますよ。
対策①:生活環境を見直して事故を予防する
皮膚の内出血の一因として意外に多いのが、家庭内でのちょっとした転倒や打撲によるものです。
特に若くて活発な犬や筋力が弱くなってきたシニア犬では、ソファやベッドからのジャンプ、フローリングでのスリップなどが出血のきっかけになることがあります。
生活環境を見直す際は、以下のような環境整備が効果的です。
・フローリングには滑り止めマットを敷く
・階段にはペット用のステップを設置する
・家具の角にコーナーガードをつける
・ベッドやソファへの昇降には踏み台を使わせる
特に関節の柔軟性が落ちてくる高齢犬にとっては、安全な動線が健康寿命を延ばすカギになります。
まずは、犬の目線に立って生活環境を見直してみましょう。
対策②:毎日の健康チェックで早期発見につなげる
皮膚内出血は、症状の現れ方が非常に地味で見逃されやすくなります。
そのため、普段の観察習慣が何よりの予防策になります。
具体的には、次のようなチェックが効果的です。
・ブラッシングやマッサージのついでに皮膚の色や状態を見る
・耳の内側、お腹、足の付け根、眼の周囲などの毛の薄い部分を中心にチェック
・歩き方や座り方がいつもと違わないかを観察
・舌や歯ぐきの色も定期的に見る
ちょっとした斑点や、いつもと違う歩き方が病気の初期サインであることも珍しくありません。
毎日のふれあいを「健康チェックの時間」にすることで、病気の早期発見・早期治療につながります。
対策③:食事と栄養管理を徹底して体の内側から強化する
内出血は皮膚や血管だけの問題ではなく、体内の血液や免疫、栄養状態と密接に関係しています。
バランスのとれた食事は、血管を丈夫に保ち出血しにくい体質をつくるうえで非常に重要です。
特に意識したい栄養素は、以下の通りです。
・ビタミンC:血管の柔軟性を高め、炎症を抑える抗酸化作用
・ビタミンK:血液を固めるために必要な凝固因子の合成に関与
・鉄分・葉酸:赤血球の生成に不可欠。貧血予防に有効
・たんぱく質:細胞の修復、免疫機能の維持に必要
・亜鉛:皮膚や粘膜の修復に役立つ
食事だけでは補えない栄養素をサプリメントで補うこともできますが、過剰摂取になってしまうこともあるため、必要に応じて獣医師と相談しながら調整しましょう。
対策④:安全対策して毒物誤飲を防ぐ
気をつけていても起こってしまうのが、犬の誤飲事故です。
特に殺鼠剤(ラットサインやワルファリン系)や一部の人間用医薬品(鎮痛剤・風邪薬など)は、出血を引き起こす致命的な毒物です。
以下のような日常の工夫で事故を防ぎましょう。
・殺虫剤、除草剤は使用後すぐに片付け、犬の届かない場所に保管
・薬やサプリメントはチャック付き容器に入れて棚の中へ
・ごみ箱にはフタをつけ、キッチンや洗面所には立ち入り禁止対策を
・散歩中は拾い食いに注意し、必要なら口輪などを利用する
愛犬は大丈夫と思っていても、思わぬ事故につながることもあります。
そのため、好奇心旺盛な子犬だけでなく、成犬・シニア犬でも油断は禁物です。
対策⑤:定期的な健診で異常を早期に発見する
皮膚の内出血は、体の中の異変が外に出たサインであることが多いです。
そのため、症状が出る前から血液検査で異常を把握しておくことが、最も確実な予防になります。
定期検診の際は、以下のポイントを確認しましょう。
・若齢犬:年に1回の健康診断(血液検査、尿検査、身体検査)
・7歳以上のシニア犬:半年に1回の健診を推奨
(血小板数、凝固時間、赤血球数、肝腎機能なども確認)
「健康だから検査はいらない」ではなく、「元気な今だからこそこまめに検査する」という意識が、愛犬の健康寿命を延ばします。
特に血液疾患は症状が出るまで進行しやすいため、油断せずに定期的なフォローをおこないましょう。
まとめ:犬の内出血が皮膚に出るのは警告サイン!放置しないで早めに行動しよう
犬の皮膚に内出血が見られたとき、ただのあざと思って放置するのはとても危険です。
体内の出血や血液疾患、免疫の異常など、深刻な病気のサインであることも少なくありません。
飼い主ができる最善の対策は、「変化を見逃さないこと」と「すぐに相談すること」です。
些細な違和感でも、それが命を守るきっかけになることがありますよ。
南柏たなか動物病院では、皮膚科専門医の診察や予防接種も受け付けています。
少しでも愛犬の異変を感じた場合は、お気軽にご来院ください。
WEB・お電話からの予約優先制を取り入れており、事前に予約いただくことで待ち時間を短縮できます。
\愛犬の皮膚に心配事があるなら/