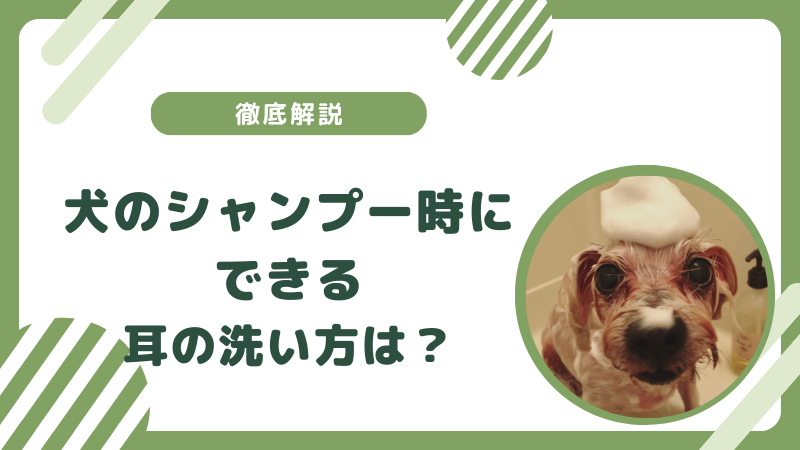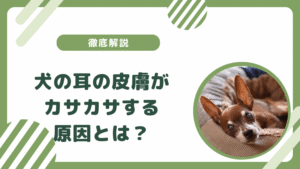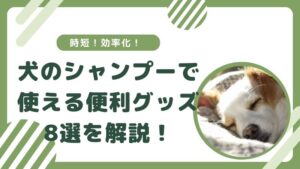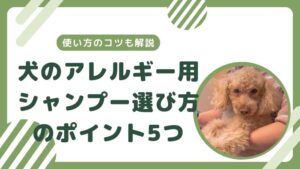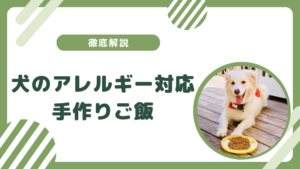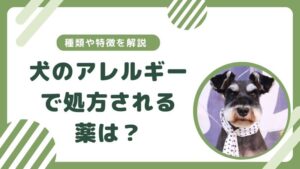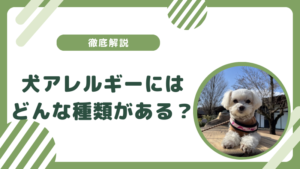「愛犬の耳はシャンプー時、一緒に洗ってもいい?」
「耳の正しい洗い方が知りたい!」
と悩んでいませんか。
犬の耳はデリケートな部位であるため、ケアを怠ると外耳炎や耳ダニのトラブルを引き起こす可能性があります。そのため、定期的なケアをしないといけません。
しかし、日常的に耳だけを掃除するのは手間がかかるため、シャンプーのタイミングで一緒にケアしたい飼い主さんもいるのではないでしょうか。
この記事では、犬のシャンプー中におこなえる耳の洗い方を初心者でもわかりやすいように5つのステップに分けて詳しく解説します。
さらに、耳トラブルを未然に防ぐためのコツや、やってはいけないNG行動についても詳しく解説します。
愛犬の耳を安全かつ清潔に保つための方法を知りたい方は、ぜひ参考にしてくださいね。
南柏たなか動物病院では、日本で数人しかいないアジア獣医皮膚科の専門医が病院訪問を担当しており、あらゆる皮膚の病気の治療が可能です。
院内は居心地の良い環境や話をしやすい雰囲気づくりを意識しており、飼い主様の不安に寄り添いながら診察しておりますので、お気軽にご相談ください。
\愛犬の皮膚に異変を感じたら/
犬のシャンプーを使った耳の洗い方5ステップ
シャンプーと一緒に耳を洗うときは、以下の5ステップでおこないましょう。
1.シャンプー前に必要なものを準備する
2.耳の中に水が入らないようにコットンを詰めておく
3.耳の表面を泡でやさしく洗う
4.泡を取り除く
5.しっかり乾かす
順に解説していきます。
耳の洗い方ステップ①:シャンプー前に必要なものを準備する
犬の耳をシャンプーと一緒に洗う際には、事前準備が非常に大切です。
準備が不十分なまま洗い始めてしまうと、泡が耳の中に入り込んでしまったり、汚れがしっかり落とせなかったりと犬にストレスを与える結果になりかねません。
基本としてシャンプーは、必ず犬用のものを選びましょう。
人間用のシャンプーは成分が強すぎたり、pHバランスが犬の皮膚と合わなかったりするため、皮膚トラブルの原因になります。
特に耳は敏感な部分なので、低刺激で無香料、洗浄力がマイルドな製品が適しています。
また、耳を洗う際には柔らかいコットンや脱脂綿を用意しておくと便利です。
ガーゼや清潔なタオルも数枚用意しておくと、洗った後の水分をしっかりふき取るのに役立ちますよ。
耳の洗い方ステップ②:耳の中に水が入らないようにコットンを詰めておく
耳の洗浄で最も注意したいのが、耳の中に水や泡が入り込まないようにすることです。
耳の中が湿ったままだと雑菌が繁殖しやすくなり、外耳炎などの病気のリスクが高まります。
特にシャンプー時は大量の水や泡を使うため、事前に適切な対策を講じておくことが重要です。
耳の入り口には、軽く丸めたコットンを詰めておくとよいでしょう。
ただし、奥まで押し込まないように注意が必要です。
また、耳の形によっても対応は変わってきます。
垂れ耳の犬は通気性が悪く湿気がこもりやすいので、洗浄後の乾燥まで特に注意が必要です。
一方、立ち耳の犬は耳の中が外気にさらされやすいため、洗浄中に泡が入りやすい別のリスクがあります。
耳の形に合わせて、最適なケアを心がけましょう。
耳の洗い方ステップ③:耳の表面を泡でやさしく洗う
耳の内部は、洗う必要がありません。
耳のケアは、表面やひだ部分など見える範囲をやさしく洗うことが基本です。
強くこすったり奥まで洗浄しようとしたりすると、かえって耳の中を傷つけてしまい嫌がる原因になってしまいます。
シャンプーは手のひらでよく泡立て、泡だけを使って洗います。
泡立てが不十分な状態で直接シャンプー液を耳に付けると、濃度が強く刺激になる恐れがあるため、泡立てネットを使ってふんわりとした泡をつくり優しく洗いましょう。
耳のひだや耳介(耳たぶ)を指の腹でマッサージするように、なでるように洗っていきます。
このとき、泡が耳の奥に入り込まないように十分注意しながら作業を進めてください。
もし犬が嫌がる素振りを見せたら、無理に続けず日を改める判断も大切です。
耳の洗い方ステップ④:泡を取り除く
耳の表面を泡で丁寧に洗った後は、その泡を確実に取り除く工程が重要です。
泡が耳に残ったままになっていると、乾燥しにくくなり皮膚が蒸れて雑菌が繁殖しやすい状態になってしまいます。
特に、シャンプー剤の成分が耳の中やひだ部分に残ってしまうと、アレルギー反応やかゆみ、赤みの原因にもなりかねません。
泡を取り除く際は、いきなりシャワーの水を耳にかけて流すのではなく、まずは濡らした清潔なガーゼやタオルで優しく拭き取るようにします。
泡が取り切れない場合は、ぬるま湯を手ですくって耳の外側をやさしく流すようにしましょう。
耳の中に水が入りそうな気配があった場合は、すぐにタオルでそっと吸い取るようにすると良いですよ。
耳の洗い方ステップ⑤:しっかり乾かす
洗浄の最後に欠かせないのが、耳をしっかりと乾かすことです。
水分が残った状態で放置してしまうと、湿度によって細菌が繁殖し、外耳炎などの耳のトラブルを引き起こすリスクが高まります。
特に垂れ耳の犬は耳の中が蒸れやすいため、乾燥不足には十分に注意が必要です。
まずは、タオルで耳全体の水分をやさしく押さえるように拭き取ります。
強くこすらず、タオルで水分を吸収させるように拭きましょう。
表面が乾いたら、必要に応じてドライヤーを使って仕上げの乾燥させます。
ただし、ドライヤーを使う際には温風を耳に直接当てないようにしてください。
風量は弱めに設定し、ドライヤーと耳との距離を15〜20cmほど保ちながら、冷風またはぬるめの風でじっくりと乾かすようにします。
また、乾かしている間に犬が耳を気にしてかいたり、頭を振ったりする場合は水分がまだ残っている可能性があります。
その際は、再度タオルやガーゼで拭き取り、しっかり乾燥させましょう。
南柏たなか動物病院では、犬や猫のあらゆる症状のお悩みに寄り添いながら診察いたします。
予約の際は、WEB・お電話でしていただくことで待ち時間が少なくすみます。
\愛犬のためには早期発見が大切/
犬のシャンプー中の耳トラブルを防ぐコツ3つ
シャンプー中の耳トラブルを防ぐ方法は、以下の3つです。
・耳に水が入らないようにする
・シャンプーが耳に入らないようにする
・垂れ耳、立ち耳でケア方法を変える
シャンプー中は水分や泡が耳に入り込みやすいため、事前の対策やケアの工夫をしてトラブルを予防しましょう。
トラブルを防ぐコツ①:耳に水が入らないようにする
犬の耳は人間と違いL字に湾曲しているため、一度水や泡が入ってしまうと自然に出てくるのが難しくなります。
その結果、湿気がこもって炎症やかゆみを引き起こし、外耳炎を発症することがあります。
洗浄時には、水が耳の中に入らないように常に意識しましょう。
シャンプー中に耳の周りを洗う際も泡をつけすぎないようにし、すすぐときもシャワーを直接当てるのではなく、手でそっと流すのがおすすめです。
また、前述のようにコットンを耳の入口に軽く詰めておくと、泡や水の侵入をある程度防げます。
トラブルを防ぐコツ②:シャンプーが耳に入らないようにする
耳に水が入ることと同じくらい注意したいのが、シャンプー剤が耳の中に残ってしまうことです。
洗浄力が強い成分が耳に残ると皮膚が刺激されて赤くなったり、炎症を起こしたりする可能性があります。
そのため、耳の周辺に使うシャンプーは泡をしっかり立ててから使用し、必要以上に量を使わないようにしましょう。
泡をつけるときも耳の穴に近づきすぎないようにし、軽くなでるような洗い方を心がけます。
すすぎの際も泡の流れに注意し、耳の方向に向けて水が流れないよう手でガードしながら丁寧に行うことが大切です。
泡のすすぎ残しを防ぐためには、最終的に清潔なガーゼでやさしく耳を拭くなど、手作業で確認しながらケアをおこなうのがおすすめです。
トラブルを防ぐコツ③:垂れ耳・立ち耳でケア方法を変える
耳の形状はさまざまで、それに応じたケアが必要です。
例えば、コッカースパニエルやビーグルのように耳が垂れている犬は、耳の中に湿気がこもりやすく外耳炎のリスクが高くなるため、洗浄後の乾燥を特に丁寧におこないましょう。
一方で、柴犬やジャーマンシェパードのように耳が立っている犬は、通気性は良いもののホコリや泡が耳に入り込みやすい傾向にあります。
そのため、洗浄時には耳の中に余計なものが入らないよう、より慎重に扱うことが大切です。
犬種や耳の形に合わせた適切なケアが、耳トラブルの回避に大きく貢献します。
犬のシャンプーで耳を洗う際のNG行動
犬の耳をシャンプー時に洗う際は、耳の奥まで洗おうとするのはやめましょう。
犬の耳はデリケートな構造をしており、無理に奥を触ると傷や炎症の原因になります。
また、シャンプー剤を原液のまま使うのもNGです。
刺激が強すぎるため、必ず泡立ててから使用し耳の中に入らないよう注意しましょう。
さらに、洗ったあとの乾燥を怠ることも避けたいポイントです。
耳が濡れたままだと雑菌が繁殖しやすく、外耳炎のリスクが高まります。
タオルで水分をしっかり拭き取り、必要に応じてドライヤーで優しく乾かしましょう。
まとめ:犬のシャンプー時の耳の洗い方はとにかくやさしく洗って清潔を保とう
犬のシャンプー中に耳を一緒に洗うことで効率よくケアができますが、正しい方法を知っておくことがとても大切です。
耳の中に水や泡が入らないよう注意し、やさしく表面を洗ってしっかりと乾かすことが基本です。
トラブルを防ぐには洗いすぎず、耳の状態をよく観察することも忘れずにおこないましょう。
もし「耳のにおいが気になる」「かゆがっている」などの異常を感じた場合は、自己判断せず南柏たなか動物病院までお気軽にご相談ください。
経験豊富な獣医師が、愛犬の耳の状態を丁寧に診察いたします。
南柏たなか動物病院では、皮膚科専門医の診察や予防接種も受け付けています。
少しでも愛犬の異変を感じた場合は、お気軽にご来院ください。
WEB・お電話からの予約優先制を取り入れており、事前に予約いただくことで待ち時間を短縮できます。
\犬の皮膚に心配事があるなら/